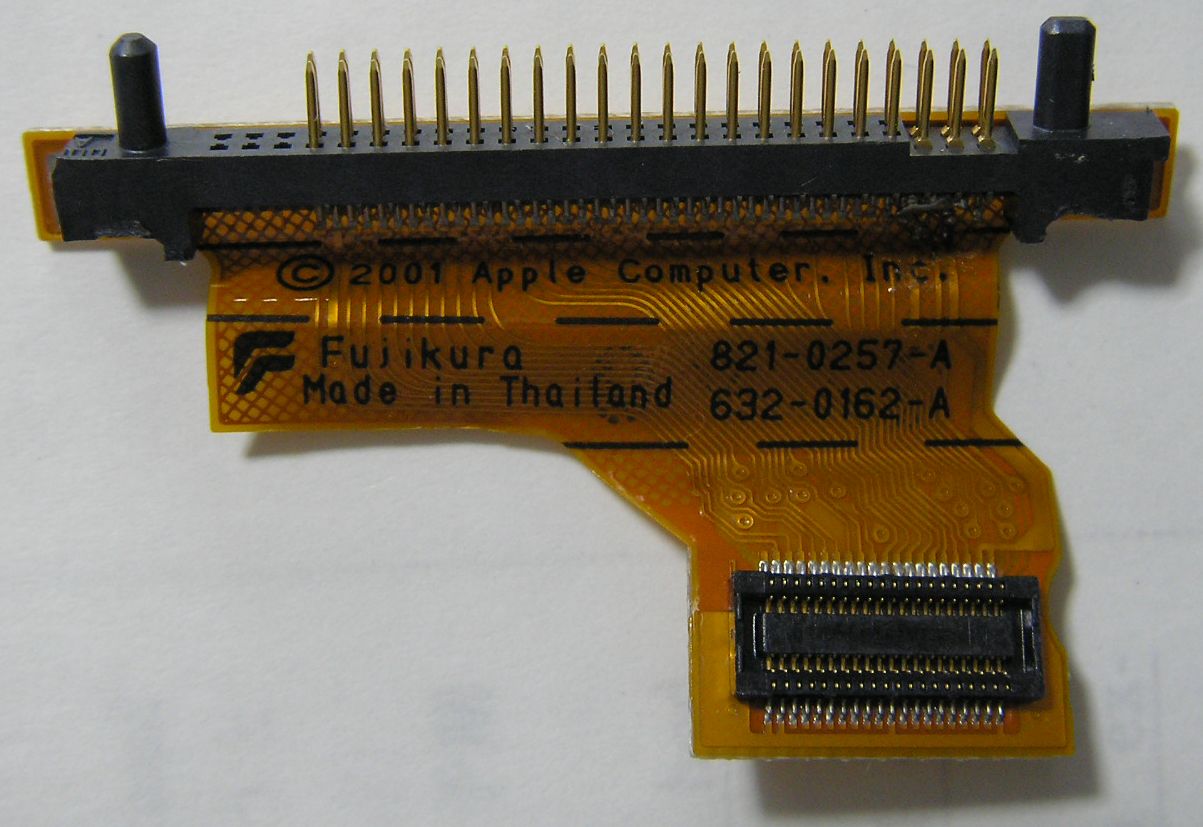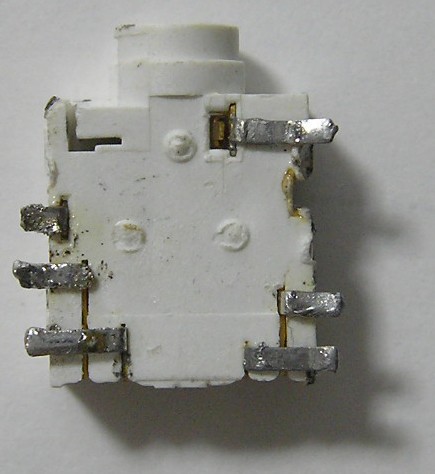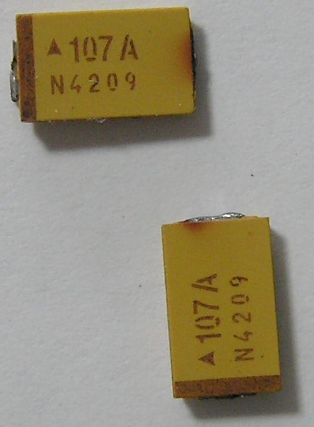第2世代iPod解体新書
私は昔、あるお方から第II世代iPodを譲っていただいた事があり、
長い間重宝していたのだが、部品の寿命なのかついに逝ってしまった・・・
壊れる前にもイヤホンジャックのゆるみだとか、ボタン・ホイール部分の異常などがあって、
その都度自分で直さなくてはならなかった。修理にはiPodの分解が不可欠である。
そこで、普段はあまり見ない(見れない?)iPodの内部を写真とともに解説しよう。
役に立つかは知らないけど(笑)。
なお開ける際、iPodはやさしく扱おう。
無理な力を加えたりすると元に戻らなくなってしまったりして、
iPodがかわいそうだぜ。
iPodを開けよう
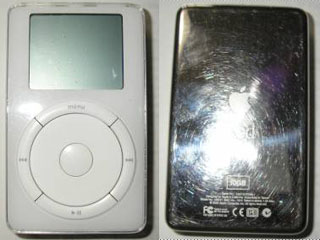
これが第2世代iPod。第1世代と外見は変わらないが、
内部がかなり変更されているらしい。容量が10GBや20GBのものが出ているようだ。
さて分解方法だが、自分がよく用いた方法は、
細いマイナスドライバーをわずかな隙間に突っ込んで広げる、
というもの。しかしこれは傷が付いてしまう方法なので、
ギター用の硬いピックを使って開けても良い。
 |
図は細いマイナスドライバーをプラスチック部分と金属部分の隙間に入れ、
こじ開けたところ。傷がつきそうだが、上手くいけば全く傷つけずに開ける事ができる。
また,指の力で金属部分を歪めて開ける事も出来るそうだが、自分はできなかった・・・
|
 |
金属の裏カバーを開けて、iPodが開いた所。金属カバーは内部側にも美しい光沢があるのだ。
両サイドに突起があり、これでiPod本体と連結している。
一方、iPod側は銀色のものが乗っかっているが、これはバッテリーである。
これを外すと内蔵ハードディスクが見えるようになるぞ。
|
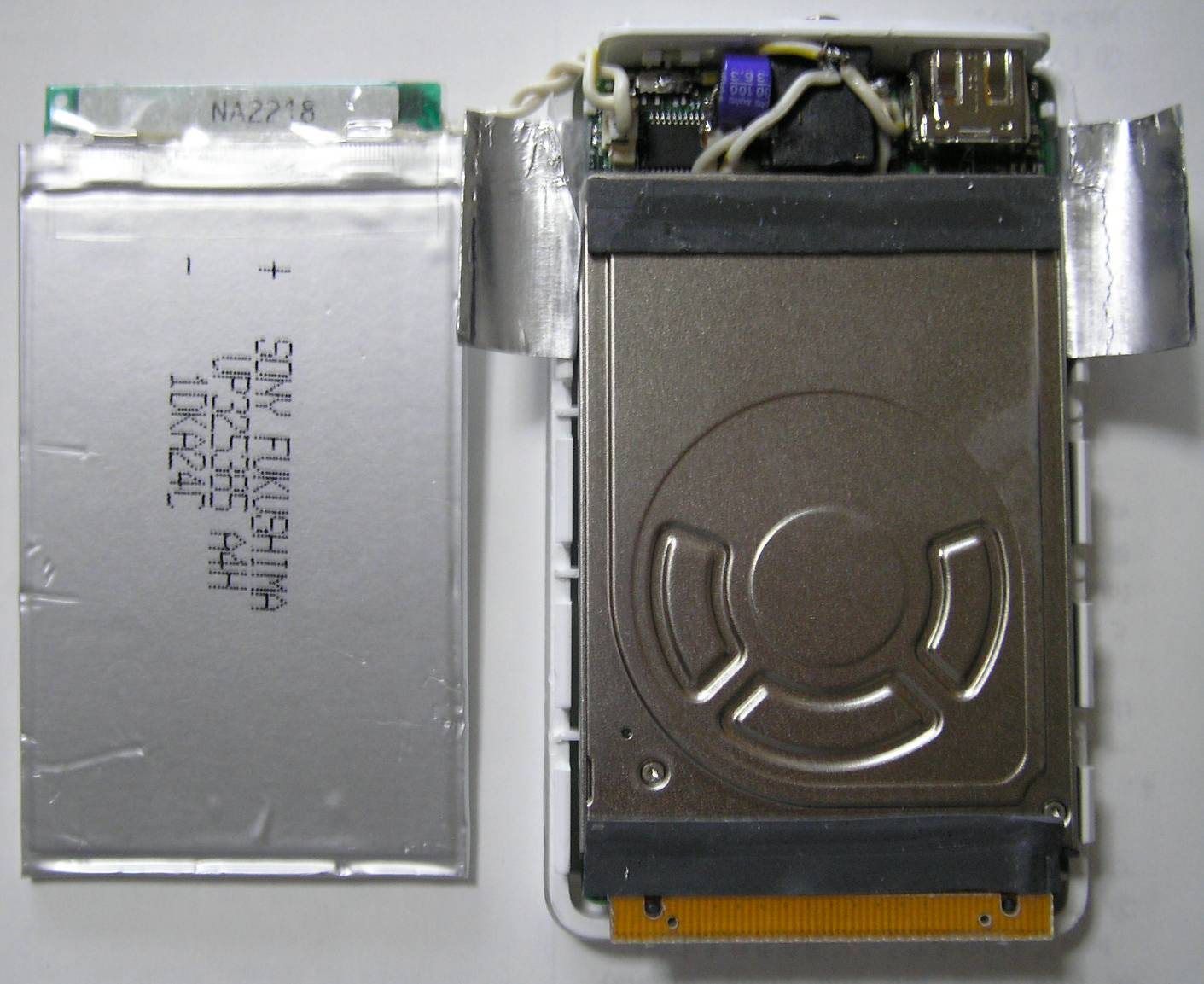 |
内蔵HDDとバッテリー。HDDは10GBのものだ
(最初に見たとき、こんなサイズで10GB入るなんて!と驚いた)。バッテリーは、
中央の表記から判断するとSONY製のものであろう。出力は約1300mA。
電圧は測り忘れた・・・スマソ。
|
 |
内蔵HDD。メーカーは東芝、型番はMK1003GAL。
この超小型1.8インチHDDは、ノートPC用PCMCIAカード型の外部HDDとして
登場したらしい。実際にPCMCIAカード端子とこのHDD端子を比較すると、
確かに一致した。容量は10GB、回転数は4,200rpm、消費電圧・電流はそれぞれ、
DC3.3V、500mAとなっている。詳細は
メーカーのページ
に書いてあるぞ。
|
Welcome to inside
それでは、iPodの内部を見てみよう。
一部、自分で修理・改造してオリジナルとはちょっと違う部分があるが、
基本的には同じだぜ。まずは裏面から見ていこう。
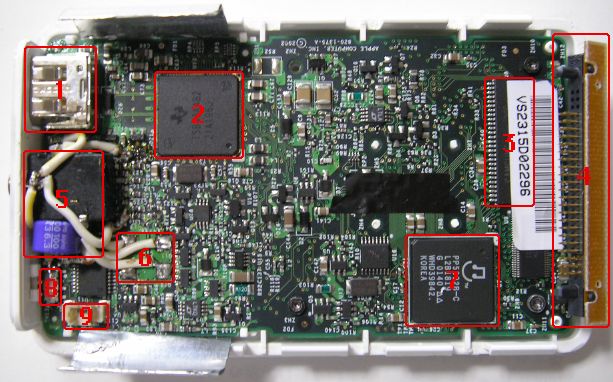
| 1:FIREWIRE(IEEE1394)ジャック |
ここを経由してデータ送受信が行われているんだな。FIREWIREの高速転送技術で転送も速い。
|
| 2:FIREWIREコントローラ・チップ |
こいつがないとFIREWIREに関する動作ができない。
ちなみにデータ読み書き中にiPodが異常に発熱するのは、
HDD以外にこいつの放熱性が悪いという噂がある。この状態でiPodを起動し、
Macと接続してデータ読み書きをした所、確かに熱かった。フーフー!!
|
| 3:システムメモリ |
バッファ用であろう。SAMSUNG製。
iPodはHDDから読み出した曲データをここに一時的に溜め込んで、ここから再生する。
そのおかげで、iPodの内蔵HDDに頻繁にアクセスすることが無くなり、
HDDクラッシュを未然に防ぐことを可能にしている。
|
| 4:HDD接続フラットケーブル | |
| 5:イヤホンジャック | |
| 6:出力用コンデンサ | |
| 7:CPU |
PortalPlayerというメーカーのチップで、MP3のデコードなどの様々な役割を果たしている。
このCPUのコードや構造を解析すれば、独自のアプリケーションを作る事が可能らしい。
80~100MHzくらいで動作する。最近では、iPodでLinuxを動かす「iPod Linux」
なるものが出現しているぞ。
|
| 8:ホールドスイッチ |
この超小さなつまみに、プラスティックのホールドスイッチがはまって
動かせるようになる。スイッチの金属部分はアースに繋がっている。
|
| 9:バッテリ接続用端子 |
ここにバッテリのケーブルを繋いで電源を供給するのだ。
とても小さいので、無理して引き抜いたり押し込んだりすると、すぐに折れてしまうぞ。
|
さて、この基盤は取り外せる。普通は外す必要はないが、この際だから全部外してしまった。
外し方には、ちょっと削ったり専用の工具が必要になるが、決して難しいものではないぞ。
 |
まず、中央に4つの白い点があるだろう。この図は既に削ってしまったものだが、
本来はリベットのように熱着固定が施されてある。カッターナイフかニッパーで削ろう。
基盤は絶対に傷つけるなよ!断線する恐れがある。。。
|
 |
図の赤丸の付いた場所に固定ネジがあるので、これを取り外すのだが、
「トルクスドライバー」という先端が星形の特殊ドライバーがないと回せない・・・
が!なんと模型用などの小型六角レンチでも回せるのだ。自分が良く使ったのは1.30mmのレンチ。
ネジ穴は以外ともろいので、無理に力を入れて回さないようにしよう。
|
これで取り外す準備は完了だ。両脇から出ている銀色の帯を持ち上げると上手く外れる。
そして基盤を取り外せば、表面の登場だ。
そして基盤を取り外せば、表面の登場だ。

| 1:圧電スピーカ |
iPod操作の「クリック音」は、ここから出る。
クリック音はどこから鳴っているんだろう?と疑問に思っていたが、
こんな部品からだとは予想もしなかった。
|
| 2:フラッシュROM |
これは推測である。メーカーはSHARP製。もしフラッシュROMなら、
iPodのファームウェアデータはここに格納されるのだろう。
|
| 3:フォト・トランジスタ |
スクロールホイールの動きを読み取るものだと思われる。
ホイール部分を分解してみると分かるが、裏側にはたくさんの切れ目が入った部分があり、
その切れ目部分はフォトトランジスタの間を通る。ボール式マウスと同じ機構を取っているのだ。
|
| 4:液晶パネル |
最近のiPodは、カラー表示ができる液晶パネルが搭載されている。
旧世代はモノクロ1ビットのみの表現力だが、それもまた味があって良い。
またこの液晶パネルは外せるが、中には黒い絶縁テープが貼ってあるだけであった。
|
| 5:ブレーキ・ゴム |
これはオリジナルにはついていないものだ。
昔、電車に乗っていたときにちょっとの衝撃でホイールが回ってしまい、
音量がMAXになる事があった。このゴムをこの位置に張り付けてやると、
スクロールホイールの回り方が硬くなり、勝手にホイールが回らなくなるぞ。
|
| 6:アクションスイッチ |
全部で5個。このスイッチの上にプラスティックのボタンが被さる。
意外と壊れやすいので、ボタンが反応しづらくなったら、このパーツを疑おう。
しかし自分で修理しようとしても、この超小型スイッチに代われるパーツは
どこにも売ってないので、自作スイッチとか作らない限りは難しいだろう
(素直にApple修理サービスに頼もう)。
|
| 7:HDDコネクタジャック |
垂直に引き抜くと外れる。フラットケーブルを引っ張らない事!ケーブルが剥がれて、
取り返しの付かないことになりかねない。あと、HDDのアクセスに異常が起きたら、
これを強く押し込んでみよう。単にここが外れているだけかも知れないからね。
|
| 8:ホールドスイッチ |
この超小さなつまみに、プラスティックのホールドスイッチがはまって
動かせるようになる。スイッチの金属部分はアースに繋がっている。
|
| 9:液晶パネル用ジャック |
垂直に引き抜くと外れる。フラットケーブルなど精密部品も結構あるので、
あまり外さない方がいいだろう。
|
以上が、内部構造の全てである。
Inside of Scroll Wheel
スクロールホイールも面白い構造をしている。分解は簡単、
ガムテープなどをホイール部分にべたっと張り付け、引きはがすと簡単に外れる。
本体を分解したならもう既に外れているかもしれない。

|
スクロールホイールはなぜ、あんなに滑らかに動くのだろうか?
その秘密は内蔵のボールベアリング。こいつがホイール部分ときっちりはまって回転するのだ。
裏側はこんな感じだ。
中央のボタンは、内部スイッチの上に来るようになっている。
なお図の右下の小粒は、内部スイッチを押すためのパーツ。
|
バッテリーの正体
バッテリーケーブル付近は特殊なシートが接着されていて中が見えない。
だがバッテリケーブルがちょん切れてしまい、再配線するときがあって、
修理箇所を透明なテープで保護したので今は中を見る事ができる。
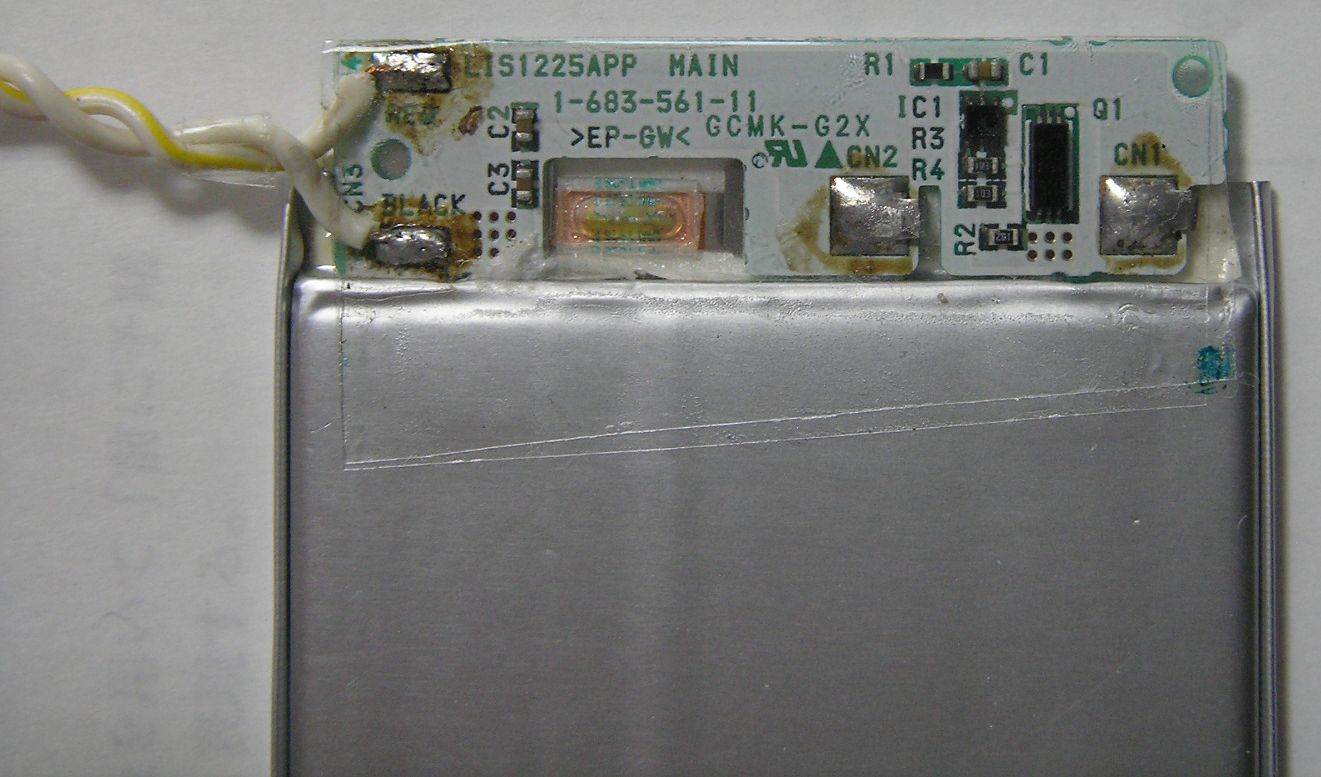
|
このバッテリーには安全回路が設けてあり、バッテリーの過放電・過充電を阻止している。
あと、配線が切れてしまって交換することになったら、
ヨリ線コードはやめておいたほうがよい。ハンダメッキしたヨリ線は太くなるので、
電源ジャックへの組み付けが非常に困難になってしまうぞ。
|
備考
iPodの中身は以上である。しかしこれは第2世代であって、
新世代機種はもっと複雑な構造になっているそうだ。
タッチ式ホイール・ボタン、カラー液晶、DOCKジャック・・・
さらにこれより小型の「iPod Mini」も出現して、精密度が増している。